Q 9 事前通知方法が変更されました
平成26年7月1日から、税務調査の事前通知方法が変更になりました。具体的には、税務代理権限証書が様式変更になり、チェックを入れておくと、税理士に先に事前通知がなされることで統一されました。
平成26年7月から施行されている条文を確認しておくことにします。
国税通則法第74条の9第5項 では
「納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合として財務省令で定める場合に該当するときは、当該納税義務者への第1項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。」
となっています。
税理士法第34条第2項では
「前項の場合において、同項に規定する申告書を提出した者の同意がある場合として財務省令で定める場合に該当するときは、当該申告書を提出した者への通知は、同項に規定する税理士に対してすれば足る。」 となっています。
これらの変更に関する、通則法通達の改正は下記です。
3章 法第74条の9〜法第74条の11関係(事前通知及び調査の終了の手続)
第5節 税務代理人に関する事項
(税務代理人を通じた事前通知事項の通知)
7-1 実地の調査の対象となる納税義務者について税務代理人がある場合における法第74条の9第1項の規定による通知については、同条第5項に規定する「納税義務者の同意がある場合」を除き、納税義務者及び税務代理人の双方に対して行うことに留意する。
ただし、納税義務者から同項各号に掲げる事項について税務代理人を通じて当該納税義務者に通知して差し支えない旨の申立てがあったときは、当該税務代理人を通じて当該納税義務者へ当該事項を通知することとして差し支えないことに留意する。
(注)
1. 1 同項に規定する「納税義務者の同意がある場合として財務省令で定める場合」には、平成26年6月30日以前に提出された税理士法第30条《税務代理の権限の明示》に規定する税務代理権限証書に、同項に規定する同意が記載されている場合を含むことに留意する。
2. 2 ただし書きによる場合においても、「実地の調査において質問検査等を行わせる」旨の通知については直接納税義務者に対して行う必要があることに留意する。
3. 3 法第74条の9第6項に規定する「代表する税務代理人を定めた場合」、当該代表する税務代理人に対して通知すれば足りるが、同項に規定する「代表する税務代理人を定めた場合」には、平成27年6月30日以前に提出された税務代理権限証書に、代表する税務代理人が定められている場合も含むことに留意する。
(税務代理人からの事前通知した日時等の変更の求め)
7-2 実地の調査の対象となる納税義務者について税務代理人がある場合において、法第74条の9第2項の規定による変更の求めは、当該納税義務者のほか当該税務代理人も行うことができることに留意する。
(税務代理人がある場合の実地の調査以外の調査結果の内容の説明等)
7-3 実地の調査以外の調査により質問検査等を行った納税義務者について税務代理人がある場合における法第74条の11第2項に規定する調査結果の内容の説明並びに同条第3項に規定する説明及び交付については、同条第5項に準じて取り扱うこととしても差し支えないことに留意する。
(法に基づく事前通知と税理士法第34条《調査の通知》に基づく調査の通知との関係)
7-4 実地の調査の対象となる納税義務者について税務代理人がある場合において、当該税務代理人に対して法第74条の9第1項の規定に基づく通知を行った場合には、税理士法第34条《調査の通知》の規定による通知を併せて行ったものと取り扱うことに留意する。
(一部の納税義務者の同意がない場合における税務代理人への説明等)
7-5法第74条の9第5項及び法第74条の11第5項の規定の適用上、納税義務者の同意があるかどうかは、個々の納税義務者ごとに判断することに留意する。
(注) 例えば、相続税の調査において、複数の納税義務者がある場合における法第74条の9第5項及び法第74条の11第5項の規定の適用については、個々の納税義務者ごとにその納税義務者の同意の有無により、その納税義務者に通知等を行うかその税務代理人に通知等を行うかを判断することに留意する。
また同時に、事務運営指針も改正になっています。
「調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)」
のうち、「第2章 基本的な事務手続及び留意事項」「2 事前通知に関する手続」が該当箇所になります。
2 事前通知に関する手続
(1) 事前通知の実施
納税義務者に対し実地の調査を行う場合には、原則として、調査の対象となる納税義務者及び税務代理人の双方に対し、調査開始日前までに相当の時間的余裕をおいて、電話等により、法第74条の9第1項に基づき、実地の調査において質問検査等を行う旨、並びに同項各号及び国税通則法施行令第30条の4に規定する事項を事前通知する。
この場合、事前通知に先立って、納税義務者及び税務代理人の都合を聴取し、必要に応じて調査日程を調整の上、事前通知すべき調査開始日時を決定することに留意する。
なお、事前通知の実施に当たっては、納税義務者及び税務代理人に対し、通知事項が正確に伝わるよう分かりやすく丁寧な通知を行うよう努める。
(注)
1 納税義務者に税務代理人がある場合において、当該税務代理人が提出した税務代理権限証書に、当該納税義務者への事前通知は当該税務代理人に対して行われることについて同意する旨の記載があるときは、当該納税義務者への事前通知は、当該税務代理人に対して行えば足りることに留意する。
2 納税義務者に税務代理人が数人ある場合において、これらの税務代理人が提出した税務代理権限証書において、代表する税務代理人の定めがあるときは、これらの税務代理人への事前通知は、当該代表する税務代理人に対して行えば足りるが、当該代表する税務代理人以外のこれらの税務代理人(以下「他の税務代理人」という。)への事前通知は行われないため、他の税務代理人へ通知事項を伝えるよう当該代表する税務代理人に連絡することに留意する。
3 納税義務者に対して事前通知を行う場合であっても、納税義務者から、事前通知の詳細は税務代理人を通じて通知して差し支えない旨の申立てがあったときは、納税義務者には実地の調査を行うことのみを通知し、その他の通知事項は税務代理人を通じて通知することとして差し支えないことに留意する(手続通達7-1)。
(2) 調査開始日時等の変更の求めがあった場合の手続
事前通知を行った後、納税義務者から、調査開始日前に、合理的な理由を付して事前通知した調査開始日時又は調査開始場所の変更の求めがあった場合には、個々の事案における事実関係に即して、納税義務者の私的利益と実地の調査の適正かつ円滑な実施の必要性という行政目的とを比較衡量の上、変更の適否を適切に判断する(手続通達4-6)。
(注) 税務代理人の事情により、調査開始日時又は調査開始場所を変更する求めがあった場合についても同様に取り扱うことに留意する(手続通達7-2)。
(3) 事前通知を行わない場合の手続
実地の調査を行う場合において、納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他国税庁、国税局又は税務署がその時点で保有する情報に鑑み、
- 違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれ
- その他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
があると認める場合には、事前通知を行わないものとする。
この場合、事前通知を行わないことについては、法令及び手続通達に基づき、個々の事案の事実関係に即してその適法性を適切に判断する(手続通達4-7、4-8、4-9、4-10)。
(注)
1 複数の納税義務者に対して同時に調査を行う場合においても、事前通知を行わないことについては、個々の納税義務者ごとに判断することに留意する。
2 事前通知を行うことなく実地の調査を実施する場合であっても、調査の対象となる納税義務者に対し、臨場後速やかに、「調査の目的」、「調査の対象となる税目」、「調査の対象となる期間」、「調査の対象となる帳簿書類その他の物件」、「調査対象者の氏名又は名称及び住所又は居所」、「調査担当者の氏名及び所属官署」を通知するとともに、それらの事項(調査の目的、調査の対象となる税目、調査の対象となる期間等)以外の事項についても、調査の途中で非違が疑われることとなった場合には、質問検査等の対象となる旨を説明し、納税義務者の理解と協力を得て調査を開始することに留意する。
なお、税務代理人がある場合は、当該税務代理人に対しても、臨場後速やかにこれらの事項を通知することに留意する。
となっています。
ここに記載ある通り、「当該税務代理人が提出した税務代理権限証書に、当該納税義務者への事前通知は当該税務代理人に対して行われることについて同意する旨の記載があるときは、当該納税義務者への事前通知は、当該税務代理人に対して行えば足りることに留意する。」となります。
簡単にいえば、税務代理権限証書に「調査の通知は税理士に連絡」とあれば、税理士に事前通知がくることになったわけです。
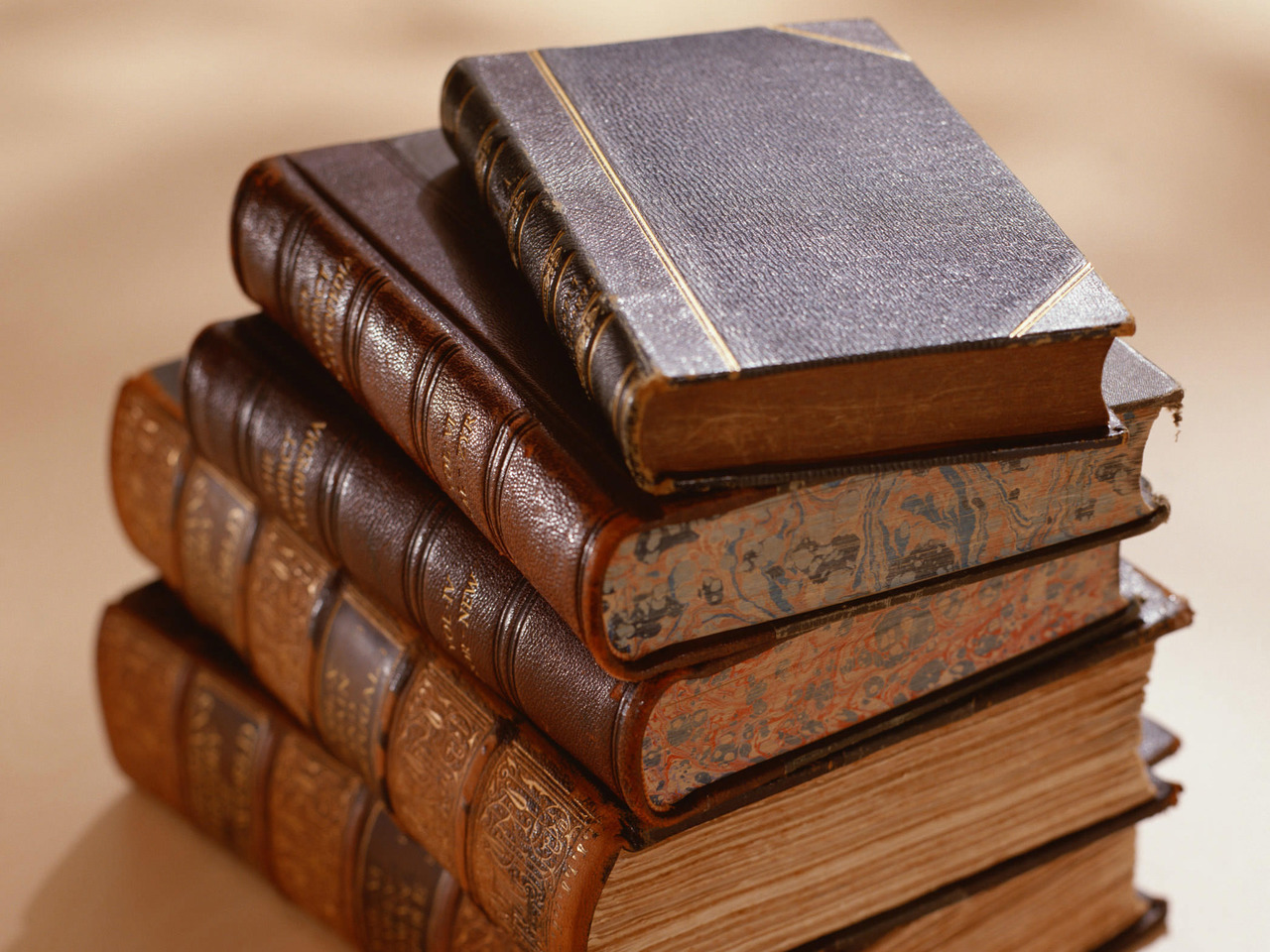



![090420_shibata-office_header[1].jpg](/_p/acre/25885/images/pc/61ab2a75.jpg)
